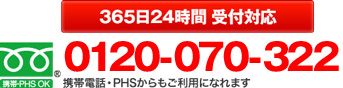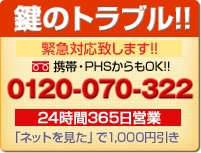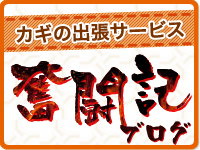2024年12月11日に、自民、公明、国民民主の3党による幹事長会談で、ガソリンの暫定税率を廃止することで合意したと発表しました。
しかし、実際のところ具体的にいつ廃止されるかは正式には決まっていません。
ガソリンにかかる税金、暫定税率が廃止避けることでガソリン価格はどのくらい安くなるのか、また、暫定税率について、歴史も含めて紹介します。
ガソリンにかかる税金

ガソリン税は、1Lあたり本則税率分で28.7円+暫定税率分25.1円+石油税2.8円課せられています。
店頭価格表示レギュラーガソリン1Lあたり180円の場合、本体価格163.6円、ガソリン税合計56.6円+消費税16.4円になり、73円分の税金が課せらされています。
ガソリン1Lにかかる税金は4割を超えていることになります。
ディーゼル車に使用する軽油の場合は、ガソリン税のかわりに軽油取引税が課せられています。
税額は32.1円で、そのうち17.1円分が暫定税率にあたります。
暫定税率が廃止されることでガソリン価格は25.1円+消費税分、軽油価格は17.1円+消費税分が引き下げられます。
暫定税率とは
暫定税率は通常の税率よりも高い一時的な税率です。
1974年に道路整備を目的とした「道路特定財源」として課税がスタートしました。
35年以上延長され、2008年3月末で期限切れとなることから、延長する租税特措法改正案で提出されたが3月31日まで可決されず、一旦失効しました。
しかし、当時の福田内閣で衆議院にて再可決され2008年5月1日から再び復活しました。
2か月間のみガソリン価格が25円以上引き下げられました。
特定財源から一般財源化
2008年に政府は、道路特定財源の一般財源化を決定し、2009年に道路特定財源制度が廃止されました。
ガソリン税が道路整備目的ではなく他の目的にも使えるようになり、「暫定的」に設けた税金のため、道路特定財源制度が廃止されたら廃止すべきとの意見も多く、暫定税率の存在意義が疑問視されました。
トリガー条項
暫定税率への批判を考慮し、2010年から「トリガー条項」を設定しました。
ガソリンの全国平均小売価格が1Lあたり160円を3か月連続で超えた場合、暫定税率分を一時的に停止し、130円を下回った際に暫定税率を復活させる内容です。
ガソリン価格高騰を抑制させる狙いがあったのがトリガー条項です。
しかし、2011年3月に発生した東日本大震災の発生に伴い、ガソリン税を復興財源として活用する目的から、トリガー条項は凍結されました。
東日本大震災から14年経過した現在も凍結は続いており、そのためガソリン価格が高騰しているにも関わらず、暫定税率が上乗せで課税され続けています。
消費税が加算!二重課税の問題

ガソリン税などを含んだ総額に10%の消費税が課せられています。
ガソリン税にさらに消費税が加算される「Tax on Tax」が問題視されています。
ガソリン税の中に含まれる暫定税率の25.1円分に2.51円分の消費税が上乗せされています。
暫定税率が廃止されることで、支払い額は、約27.6円抑えられます。
暫定税率廃止 ガソリン価格が下がるのはいつから?
ガソリンの暫定税率廃止の時期として2026年4月が有力と考えられています。
2026年度予算案をスムーズに通過させるために、暫定税率廃止を野党との取引のひとつに利用する狙いもあるのではとの見方もあります。
すぐに暫定税率が廃止にならない理由には、年間約1.5兆円の税収減になるとのことで、トリガー条項は解除されないままガソリン価格は高騰しています。
国民に負担が増える増税は直ちに実行するのはおかしい!国民の可処分所得減少はどうでもいいのか!国は決めた約束を守らず税金を徴収し続けるのはいかがなものか!などの意見も多くあります。
ガソリン税の暫定税率廃止が正式決定されガソリン価格が引き下げとなる日まで、もうしばらくの辛抱が必要です。